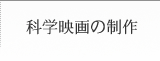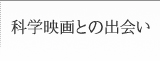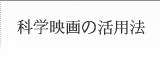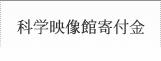- ホーム
- 科学映画の制作
- 岡田桑三について

岡田桑三について
< プロフィール >
岡田一男(おかだ・かずお)
1942年東京生まれ。全ソ国立映画大学卒。
科学映像・記録映像の演出・製作者。
東京シネマ新社代表取締役。

岡田一男
東京シネマの創業者であり、プロデューサーでもある岡田桑三(1903~1983)については、2002年に原田健一・川崎賢子の共著による克明な評伝「岡田桑三 映像の世紀 グラフィズム・プロパガンダ・科学映画」が、平凡社より出版されている。
また、彼が関わった太平洋戦争時のプロパガンダ雑誌「フロント」の復刻版刊行(平凡社)にあたって、筆者が記した生涯の概略(1990年1月初出)が、若干の改筆を加えて東京シネマ新社のホームページに掲載されている。

週刊朝日1964年12月11日号の表紙を飾った岡田桑三
岡田桑三にまつわるキーワードを整理してみると、まず80年のその生涯のうち、20年間を映画俳優、山内光として劇映画の世界で過ごしたことが挙げられる。半世紀にわたる盟友であった木村伊兵衛をはじめ、写真界や出版界にも多くの友人知人がいた。
また、10代のころよりアナーキズムに心を惹かれ、舞台美術家を志してのドイツ、ベルリンへの留学時にはマルクス主義を受容し、晩年に至るまで、紆余曲折はあったものの、その立場を捨てなかった。
しかし、もともとクリスチャンであった母親への反発から始まった批判精神と自由な発想は、教条主義への堕落から彼を救った。こうして20世紀の代表的なキーワードである「映像」と「社会主義」の双方に、彼は深く関わったのである。それらをつないでいたのは、夢であり未来への希望であった。
その人生の前半の総決算は、戦時プロパガンダ雑誌「フロント」の編集人となることであった。そこには、もともと豊かであった手持ちの人脈を総動員した。
しかし、この日本軍国主義への荷担が、後半生を複雑なものにした。1930年代の天然色写真への傾倒は、戦時における軍部との意見対立から「フロント」を退いた彼に、すぐ次の活動の場を満州に用意させた。しかし満州は、傀儡国家の崩壊、ソ連軍の占領、そして国共内戦と、敗戦国民の辛酸をいやというほどなめさせた。
敗戦後の混乱期を、出版世界で「南方熊楠全集」とアメコミ雑誌「スーパーマン」の発刊という、もう少しあとでなら成功したであろう試みで苦悶した後、たどりついたのが、1952年に始まる東京シネマにおける短編映画の製作なのであった。
10代の終わりにパリで見た、アメリカ人、ロバート・フラハティのイヌイットの暮らしを追った記録映画「ナヌーク(極北の怪異)」や、20代後半にモスクワで見た、ソ連ドキュメンタリー映画に触発された非劇映画への志向が、ここで花開いた。初期の東京シネマ作品を見れば、新しい表現メディアであるカラーフィルムを駆使した短編映画としての新鮮な感覚は見て取れるが、必ずしも生命科学の映像化を標榜するプロダクションではなかったことが見て取れる。
しかし時代は、本人の予想以上に、素晴らしい土俵を用意していた。
日本経済は、悲惨な戦争からの回復期に入ろうとしていた。戦後の最悪の時期を岡田桑三は、公職追放の身であった澁澤敬三を担いで、南方熊楠の全集刊行に奔走したが、それは経済的には不遇であっても、人文系、自然系双方の学問世界の人脈を豊かに広げ、その一端は経済界にも繋がっていた。その豊かな土壌が苦難の時代に用意されたのだった。
加えて世界的にも短編非劇映画は、かつてなかった黄金期を迎えようとしていた。その中で世界標準に通じる先端的な研究を映像化することの意味を直感的に、いち早く把握し、余人に先駆けて展開することができた。
東京シネマが、その威力を発揮したのは、1954年から1966年までの、たかだか12年に過ぎないが、この間にはプロデューサーである岡田桑三とシナリオライターである吉見泰、そしてカメラマン小林米作の、結果的に見ると豊かな協同作業があった。「ミクロの世界」や「生命誕生」に見られる、時間を追って変化していく事象への執拗な追求が、大きな意味を持つ作品には、特に威力を発揮した。
しかし、その取り扱う領域を広げようとすると、それはそれほど簡単ではなかった。東京シネマが12年間に関わった作品はおよそ100作品であるが、その多くで苦闘している。
電力会社をスポンサーとして第一歩を踏み出した東京シネマは、比較的に楽な一歩を踏み出したのだが、石油会社・丸善石油による「マリン・スノー」「潤滑油」「ガソリン」や、家電メーカー・松下電器産業による「パルスの世界」「結晶と電子」などをスポンサーとして科学映像を作るには、構成も工夫を要した。CGのない時代に安易にアニメに逃げるのを潔しとしなかった作風は、苦労を倍増させた。素直に対象を追うことで成功した作品としては、ヤクルトのスポンサードによる「選ばれた乳酸菌」ぐらいしか挙げられない。
それでも苦闘の成果は、東京シネマ作品をひと味もふた味も違う、他社の作品と際だったものにしているといえよう。これは同時代の、たとえば岩波映画や日映科学の作品とも異質であるし、東京シネマから離れていった人々が作ったヨネプロダクションや、シネサイエンス(現在のアイカム)の後の作品群とも異質である。たぶん、そこにプロデューサー、岡田桑三の強烈な個性が存在したからだ、と筆者はとらえる。製薬会社をスポンサーとする医学映画を作るというのは、科学映像の小さなジャンルに過ぎない。それを広げようとした挑戦が、岡田桑三と東京シネマには存在したのである。
2006年の夏、前年末に100歳で他界した小林米作の追悼のイベント「科学映画と音楽の午後」で、参加者にお配りする記念DVDに東京シネマからお出しする作品として、私はあえて「生命誕生」ではなく「ガソリン」と「結晶と電子」の2作品を選んだ。
この2作品は、失敗作と言えば言葉が過ぎるが、東京シネマの最高傑作ではない。私は、大先輩であるカメラマン小林米作を敬愛はするが、美辞麗句でおくるという意思はこれまでもなかったし、これからもない。しかし、これらの作品における小林米作の苦闘の跡を、多くの人々に見てもらいたかったのだ。それは、ある意味で、ついに小林米作が自分の会社、ヨネプロダクションでは再び取り組むことのなかった分野でもあった。
最後に、1966年に小林米作らが去った後の東京シネマと岡田桑三についても触れておこう。
1961年から66年まで、筆者自身はモスクワの全ソ国立映画大学(VGIK=現在は全露国立映画大学)に留学し、リベラルな世界観の持ち主として知られたミハイル・ロンム監督を主任教授とする劇映画演出のコースに在学していた。
ここから筆者は映画の世界に身を置くことになったのだが、モスクワ在学中は、必ずしも科学映画に専念するという意識はなかった。ただ、5年間にわたって父親と文通を続ける中で、東京シネマが抱える多くの矛盾や悩みを父親と共有することになっていった。そして、必須科目を修了した直後に帰国して父親を支える決断をした。
1966年に経済的な困難に加えて、東京シネマ内部の葛藤は極に達した。これに対して、岡田桑三本人の決断もあったが、筆者は、実質的に東京シネマをいったん解体して、新たに出直すことを強く主張した。
移行期の作品には、製作体制にも妥協があったが、東京シネマ新社が確立したとき、旧東京シネマの製作スタッフは誰も加えず、しかも製作スタイルも大きく変わったプロダクションとして再生を遂げた。試行錯誤で変えていった部分もあるのだが、最も大きく異なるのは、自前のスタジオを持たないと決めたことである。そして、いかなる制作環境でも撮影体制を組めるよう、機材編成を考えていった。
当然ながら旧東京シネマの多くを検討したが、それ以上に、西独ゲッティンゲンの科学映画研究所(IWF)の機材編成や製作スタイルを参考にした。それはもう1つ、1970年に本格化した、学術研究映像、高等教育映像の国際的な収集運動、エンサイクロペディア・シネマトグラフィカ(EC)の日本支部の立ち上げと、その後の運営に参画したこととも結びついている。
この中で、ほとんど同じ中心スタッフでミクロ映像も撮れば、スキューバを使った水中撮影もやるし、フィールドに出ては野生動物を追いかける自然誌映像を撮るし、伝統芸能や民俗的な儀礼の記録も、民族問題に関わるドキュメンタリーまでを、同列に扱うプロダクションに変貌した。
それらの仕事の初期に、老齢になった岡田桑三も積極的に関わり、必死で若いスタッフについてきて、さまざまなアドバイスを残してくれた。その死後、25年になろうとする今でも、彼のし残した仕事の一部を筆者たちは続けている。
その彼の人生の締めくくりとなったのは「マリン・フラワーズ 腔腸動物の生活圏」の製作である。発端は、昭和天皇の生物学研究に触れ、ヒドロゾアの生態に関心を持ったことであるが、これは東京シネマを始めるより前の、出版世界に身を置いていた1950年代初期のことだ。それ以来20年間以上、その実現を夢見続けた。
評伝執筆のため、さまざまなインタビューを果たした原田健一は、桑三と親密だった民族考古学者、江上波夫に岡田桑三について尋ね「夢の多い人だった」と聞かされている。
敗戦直後の満州で一時期彼らは同居していた。1つの布団を男3人でシェアする中で、1人が赤痢を患って死亡し、伝染を恐れた江上は、桑三手持ちのアクリノール錠剤を一晩で一瓶、食ってしまったという。そんな悲惨の極みといった状況の中でも2人は、日本帰国後の壮大な夢を語り合っていた。
2人して三笠宮殿下をいただいて、応仁・仁徳天皇陵の発掘調査を実現しよう。発掘の総指揮は江上が担当し、映像による記録は岡田が指揮を執る、その資金源には糸魚川の翡翠を掘ろうという途方もない夢物語であった。いろいろな夢を持てる人間は幸せだ。
岡田桑三の人生は、さまざまな夢を見ては実現に向かって突進し、その一部では事実、輝かしい成功を勝ち得、その後に壮烈に挫折し、次の飛躍への苦闘を繰りかえすというものであった。幸いなことに、多くの友人・知人が挫折した彼を必ず救い出した。苦境の中にも、次への夢を見ることのできたのが岡田桑三であった。科学映像館で紹介されるいくつかの映像は、その夢の痕跡なのである。